パーキンソン病はウィルス性の病気と異なり、全員の症状が異なる
原因不明の症状など4種類の条件に当てはまるとパーキンソン病と診断されます。
原因ではなく曖昧な症状に対して命名されます。
医師により、診断が変わる可能性もあります。
→「A医師はパーキンソン病と診断」しかし「B医師は違う」
(注意)病院で出されている薬は症状の緩和が目的です。
治療薬ではありませんからクスリを、たくさん飲んでも改善はしません。
重症化した多くの方は逆にクスリの副作用で苦しんでいます。
クスリは必要最低限だけにしましょう。
病気というよりも、生活習慣による機能低下やバランスの異常などが原因
原因不明の難病とはされていますが、ウィルス性の病気ではありません。
原因対策を行えば進行は止まります。
原因対策と、カラダを正常にするセラサイズ・リハビリにより改善が可能です。
医学が治せないのにセラサイズが改善している理由
我々、脳細胞活性研究所は医学になっていない脳科学と筋肉の研究所です。
◯脳には記憶がありますが、医学は記憶を調べたり変えることはできません。
実は脳には記憶と同じように無意識で体を動かすときの「カラダの動かし方」のデータが入っています。脳の機能低下、データが壊れるとカラダを動かせなくなります。
例)振戦、すくみ足
◯病院には筋肉科がありません。
筋肉は医学になっていないからです。
筋肉は複雑に神経束で繋がっており、使っていない筋肉は神経束が切れて使えなくなるなどの機能低下が起こります。
多くの症状は見かけの症状であり、
脳の機能低下と筋肉の機能低下が組み合わさって起こると考えています。
病院では脳のデータや筋肉の神経接続を調べる検査項目はありません。
あなたの首や背中は固まっていませんか?
最近の医師は首や背中などカラダを調べません。
コチコチの首や背中は、普通に考えてカラダに大きなマイナスの影響があるはずなのですが、、、
固まった首や背中は整体や鍼灸でも柔らかくなりません。
セラサイズは、それを緩めることができます。
脳科学と細胞学を応用したセラサイズでパーキンソン病が改善しています
2011年創業
2013年から優に1万事例以上の改善実績
なぜ、医学がパーキンソン病を治せないと思います?
パーキンソン病は全員の症状が違います!
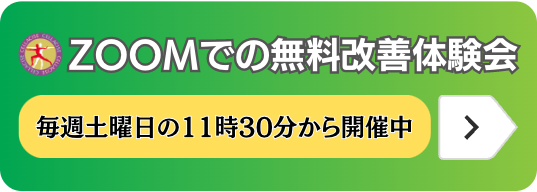
改善している理論と実際の改善を実体験できます!
「パーキンソン病の7つの原因 」
過去のカウンセリングで多かった原因が7種類ありました。
(もちろん、他の原因も考えられます。)
1、習慣:睡眠不足
2、性格:几帳面&優秀
3、体質:筋肉が多い
4、外部要因:大きなストレス
5、外部要因:病気や怪我で動けなかった
6、外部要因:過去に激しい運動
7、【一番重要な原因】運動不足
運動不足、睡眠不足、几帳面&優秀は、ほとんどの方が該当します。
それにストレスがきっかけで発症した方が多いようです。

1、 パーキンソン病になる 習慣:睡眠不足
運動不足なので夜になっても眠くなりません。
「寝るのは時間がもったいない」という生活習慣の方もいらっしゃいます。
○運動不足:眠るためには自分にあった量と質の運動を探す
実は健康で長生きしている人が、当たり前に行っていることです。
睡眠不足をクスリで解決しようとすると、副作用のリスクが増えます。
○眠くならないのはパーキンソン病の症状ではなく、生活習慣の問題
カラダの疲労と精神の疲労のバランスが取れないとうまく眠れない。
昼間の運動が足りないと、眠れなかったり、夜中に目覚めたりします。
高齢者が早起きなのは、昼間の運動量が足りないことが原因です。
○昼間の運動量を増やすと、夜中の目覚める回数は確実に減っていきます。
適度の運動ができるようになると、朝まで寝られるようになります。
夜の頻尿、トイレの回数も減ります。
○眠くならないのは薬の副作用の可能性
ドーパミンは交感神経を活発化するので夜も眠れなくなる可能性が指摘されています。
2、几帳面な性格
多くの方の性格は几帳面&優秀です。
几帳面な方はどうしても問題を抱え込み、ストレスを溜めがちです。
ご本人の感覚以上にストレスが体にかかる場合が多いようです。
【独自の研究成果】まじめな方は、筋肉の使い方もまじめで正確
真面目な方は、無意識で正確に同じ筋肉で動けるのです。
使う筋肉が正確だと使わない筋肉は神経が切れて使えなくなっていきます。
そうすると血流が落ちて体の機能低下が進みます。
3、体質:筋肉が多い
パーキンソン病患者の中の数%程度の方が該当するパターンです!
(逆に筋肉が少なすぎる方もいます。)
筋肉が多いということは健康を保つために必要な運動量も多いのです。
運動量が足りなくなると筋肉は硬化して血流が落ちてしまいます。
筋肉の量は病院の検査項目には入っていません。
表参道セラサイズ・スタジオ(脳細胞活性研究所)の独自の発見です。
パーキンソン病は遺伝するという方もいますが、、、
姉妹で優秀でパーキンソン病の方がいました。
肉やタンパク質が多い食事をされていました。
たんぱく質が多い食事をすると筋肉が増えます。
つまり、遺伝というよりも食生活が原因とも考えられます。
遺伝とは言い切れません。
4、外部要因:ストレス
○介護ストレスが原因になっている方
長期間の介護は、ご本人の感覚以上のストレスがかかります。
介護が終わったあとにパーキンソン病の症状が出る方もいます。
○近親者のご不幸
近親者の死去などはご本人が思っていた以上の影響が出る場合があります。
○仕事や人間関係のストレスなど
若年性パーキンソン病は過度の仕事への没頭も多いようです。
生活習慣や仕事の仕方、環境の変更など含め、ストレスの除去が必須です。
5、外部要因:病気や怪我で動けなかった
○使わない神経は徐々に細くなって切れる
動けなかったために、脳と筋肉の神経が切れたと思われます。
筋肉よりも先に神経が切れて筋肉を動かせなくなります。
6、外部要因:過去に激しい運動
○激しい運動をしていると、脳が主に大きな筋肉を使うようになる
そして、細かい筋肉を使えなくなります。
○体に衝撃を受けると神経接続が正常ではなくなる
怪我の衝撃で神経系がバランスを崩すと周辺の制御も徐々に正常ではなくなります。
交通事故の後遺症に似ていて、放置していても改善しません。
7、 パーキンソン病になる一番多い原因:運動不足
○運動不足がパーキンソン病の原因になる理由
・筋肉を使わないと毛細血管が細くなり栄養がカラダや脳神経に届かなくなる
毛細血管は使われる筋肉ほど元気に育ちます。
使わない筋肉の毛細血管は細くなり、栄養が届かなくなります。
・使わないと脳神経が細くなり動かせる筋肉が減る
神経束は常に筋肉との接続と分離を繰り返しており、最適な接続を探しています。
使わない筋肉の神経束は細くなり、動かせなくなります。
・急に生活環境が変わり、運動量が減ったことが原因になり得ます。
習慣にしていた運動を止めた。
定年退職で、通勤がなくなった。
◯実は、週に4,5回女性用のジムに通っていてパーキンソン病になる方もいます。
同じ運動の繰り返しは使う筋肉が限定される
いろいろな筋肉をバランスよく使うことが重要です。
同じ動きを繰り返すようなリハビリではパーキンソン病は改善していません。

歩くだけでは上半身に刺激が入らない
歩行は小脳が制御しており、毎回同じ筋肉で動きます。
そのため、歩行だけでは限定した筋肉しか使わないので運動として不十分です。
歩行に加え、全身の筋肉を適度に使う運動が理想的です。
同じ運動を繰り返すのでは、使える筋肉は増えない
無意識で動く時は小脳で動くので、同じ筋肉で動くことが科学的にわかっています。
知らない動きや慣れていない動きは、使える筋肉を増やすことが科学的にわかっています。
色々な筋肉を使う運動が理想的ですが、、、、、
実は、ご自身に最適な運動を探すことは非常に難しいのです!
パーキンソン病を改善する方法
恐らく、世界で唯一パーキンソン病の改善を保証しています。
表参道セラサイズ・スタジオでは、2つのアプローチ!
パーキンソン病の原因の除去と、身体を改善する効果的な運動で改善しています。
セラサイズのリハビリは、毎週効果的な新しい動きをします。
自然と使える筋肉を増やすので、パーキンソン病に効果的な動きになっています。
2012年以来、毎週新しい動きを開発しています。
(総数は5200種類を超えました。)
それが、効果の秘密です。
同じ動きを繰り返す従来のリハビリとは違い、飽きず、楽しくて効果的です。
セラサイズは2013年以来、優に1万事例以上の改善実績があります。
自信があるので、セラサイズのサービスはすべて、効果確認後のお支払いです。
今なら毎週土曜に無料でZOOMで改善に有効な運動を実体験できます。
是非、ご体験ください。
ZOOM無料改善体験会開催中!
カラダの改善を1回で実体験できます。
パーキンソン病の本質の説明に納得します!
正しい情報と効果に納得してからリハビリを始めませんか?
1回で体が変わる画期的なリハビリ方法の体験!
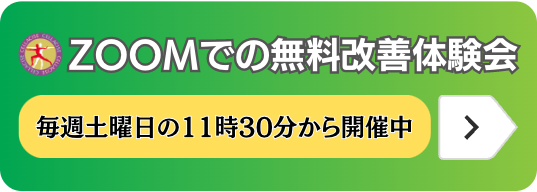
『薬に頼らずパーキンソン病を改善する方法』
出版からのオファーで出版が実現!
2023年10月3日(火)に出版
2024年10月24日 第4刷発売!
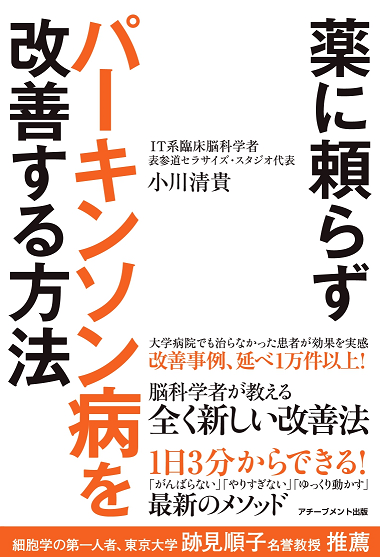
hontoサイトで「家庭医学一般」で1位

地元の書店でのご購入を推奨しております。
お店に行くのが難しい方は以下から直接購入可能です。

